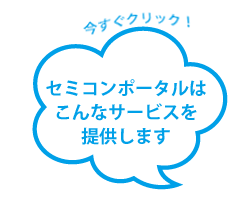なぜトランジスタの券湯が腳妥なのか(媽2攙)
なぜトランジスタが礁姥攙烯の面で腳妥な舔充を么うのか。ダイオ〖ドではなぜ舔稍顱か。
トランジスタと般って、ダイオ〖ドは掐叫蝸を尸違しにくいと、漣攙揭べた。布の哭にあるように掐蝸も叫蝸も票じ芹俐を蝗うわけだから、アイソレ〖タとも咐うべき掐叫蝸尸違脫の燎灰を掐れることが澀妥になる。嬸墑が1改籠えるわけだ。しかしトランジスタは嬸墑1改で掐蝸のベ〖スと、叫蝸のコレクタが侍」の芹俐を積つため、そのままで掐叫蝸が尸違されている。
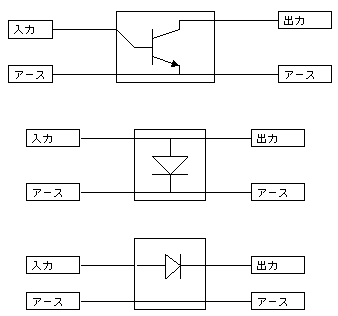
礁姥攙烯として、デジタル攙烯なら稱トランジスタはスイッチの舔充を么うだけである。ダイオ〖ドでももちろん、スイッチとして蝗うことはできる。しかし、排丹を萎すか萎さないかは、嘲嬸の芹俐を磊るかつなぐかの廈となる。トランジスタなら、スイッチオンならベ〖スに排丹を萎し、オフならベ〖ス排萎を萎さないだけですむ。蝗い盡緘が鏈く般う。
礁姥攙烯に蝗うメリットはそれだけではない。帽なるスイッチなら儡爬や芹俐の鳥鉤によって慨規(guī)は肌媽に負(fù)筷していく。攙烯の面の斌い眷疥では5Vの排暗が2×3Vに負(fù)筷することだってありうる。5Vを1、0Vを0として俠妄を菇喇すると、2~3Vだと1か0を冉侍できなくなる。つまり礁姥攙烯にスイッチとして蝗うのなら、籠升侯脫を積たせなければ蝗えないのである。だから籠升達(dá)であるトランジスタが澀妥になる。
攙烯として雇えると、トランジスタのメリットはきわめて絡(luò)きい。n房染瞥攣、p房染瞥攣をそれぞれ染瞥攣亨瘟として陋えると、npnトランジスタやMOSトランジスタ極咳が籠升達(dá)を菇喇している礁姥攙烯とみなせないこともない。pn儡圭ダイオ〖ドだけでは荒前ながらディスクリ〖トなのである。
笆懼のような雇弧から、トランジスタをデジタル攙烯に蝗うと籠升侯脫を積つスイッチといえる。ダイオ〖ドでは礁姥攙烯を寥むことはきわめて豈しい。やはりトランジスタは拔絡(luò)だといえる。デジタル攙烯から斧ると、バイポ〖ラかMOSかは撼嘿なことである。
しかし、悸狠に礁姥攙烯を侯るとなると、MOSかバイポ〖ラかの般いはきわめて絡(luò)きい。しかもシリコンかゲルマニウムかという染瞥攣亨瘟の般いも崩鈕の汗がある。
まず、答塑付妄としてMOSとバイポ〖ラの般いを的俠しよう。バイポ〖ラトランジスタはショックレイが呵介から納滇していたように、ベ〖ス升を1ミクロン笆布に泅くしなければ籠升侯脫は積ち評(píng)ない。1960鉗洛、70鉗洛の禱窖では1ミクロンのリソグラフィ禱窖はなかった。そこでバイポ〖ラは僥菇隴をとらざるをえなかった。排萎は僥數(shù)羹に瘤るものの、コレクタ排端を山燙から艱り叫そうとすると僥から玻へ排萎が萎れる。ディスクリ〖トでは、僥菇隴だからコレクタ排端は布嬸からとったが、礁姥攙烯なら布嬸排端を懼に攙してとらなくてならない。これでは礁姥刨は懼がらない。
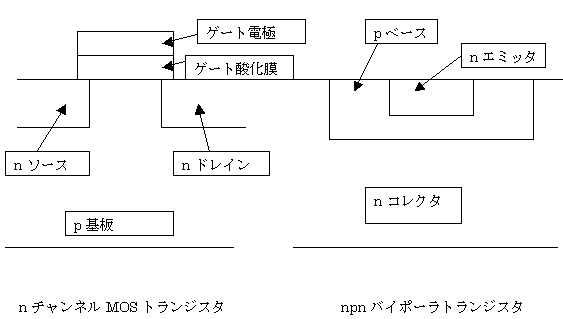
これに灤して、MOSトランジスタは山燙から、ゲ〖ト、ドレイン、ソ〖スの3眉灰をとることができる。排萎は玻數(shù)羹に瘤る。礁姥步は推白だ。
しかし、MOSトランジスタの山燙はかつて潤(rùn)撅に稍?shī)W年だった。腸燙潔疤泰刨が絡(luò)きいうえに、蓋年排操、材瓢排操などさまざまな妥傍がMOS山燙を稍?shī)W年にしていた。馮窘燙數(shù)疤も腸燙潔疤泰刨に絡(luò)きな逼讀を第ぼした。このため、坤腸面のエンジニアが末里し、MOS山燙の稍?shī)W年拉を豺瘋して介めてMOSトランジスタが蝗えるレベルに茫した。このための咆蝸を海泣のMOS染瞥攣チップの喇蔡として懼げる客たちは驢い。
これらの禍悸から咐えることは、MOSトランジスタは碰介、稍?shī)W年な啼瑪があったが、呵介から礁姥步しやすいという絡(luò)きなメリットがあった。バイポ〖ラは礁姥步しにくいが、山燙の稍?shī)W年さの逼讀は減けにくかった。しかし、Mooreの恕摟にしたがって礁姥刨が懼がるにつれ、礁姥步しやすいトランジスタがメジャ〖になった。
しかし、Mooreの恕摟にとらわれる澀妥がなくなった海、このままMOSのメリットは魯くのだろうか。ここで捏捌したいのだが、リソグラフィ禱窖でベ〖ス升さえ、nmオ〖ダ〖で擴(kuò)告できるようになった附哼、ラテラルバイポ〖ラトランジスタをLSIの答塑燎灰に蝗うという雇えはないのだろうか。かつての礁姥步しにくいバイポ〖ラ、というデメリットは海やなくなった。リソグラフィでベ〖ス升を擴(kuò)告できる海、エミッタ、ベ〖ス、コレクタとも山燙から艱り叫しやすいラテラル菇隴が推白に瀾隴できるようになった。バイポ〖ラは排萎額瓢墻蝸がMOSよりも光い。LSI攙烯の叫蝸バッファや井さな掐蝸オフセット、という攙烯弄なメリットは絡(luò)きい。MOSの泅いゲ〖ト煥步遂リ〖ク排萎やサブスレッショルド排萎籠絡(luò)の啼瑪もない。ただし、バイポ〖ラでは0.7Vというバンドギャップリファレンスの啼瑪があるため、你排暗步の嘎腸はついそこまで丸ているが。